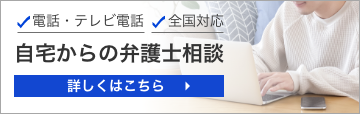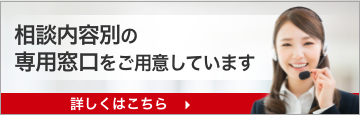取引先の社員による不正取引で受けた損害について、和解で解決した事例
- CASE1247
- 2025年05月01日更新

- 法人
- 債権回収
ご相談内容
A社はB社へ商品を販売する取引を長年継続していたところ、B社の副部長Cは、A社にB社が希望する商品を提供するD社を紹介するので、A社に間に入ってほしいとの話を持ち掛けました。具体的には、B社がA社に発注すると、A社は、そのままD社に注文をします。商品はD社からB社に直接輸送され、A社は商品価格の1割の利益を受けるというもので、A社は在庫を抱えるリスクもない魅力的な取引と判断し、話に乗りました。
取引は1年近く順調に続き、取引量も増えてきました。ところが、ある頃から、B社からA社への支払いが滞るようになり始めたのでA社がB社に問い合わせてみると、B社はそのような取引は全く知らないし、すでにCは姿をくらましていたことがわかりました。
調べてみると、CはD社と示し合わせ、社内決済無しにB社の名義で発注書をA社に送り、A社からD社に仕入れ代金が支払われると、D社からD社の手数料を引いた残額を受け取った上で、その一部をA社などへの支払いに充てて、差額を着服していました。そのようなことをすればすぐに行き詰まりそうですが、Cは、このような取引をA社以外にも多数持ち掛けて、入金と支払いをうまく自転車操業して誤魔化し、誤魔化しがきかなくなったタイミングで姿を消したのです。
未収金が数千万円にも上っていたA社は、回収しないと会社が潰れてしまうと考え、ベリーベストに相談しました。
ベリーベストの対応とその結果
A社の代理人となったベリーベストは、早速B社との交渉を開始しました。
B社は役員と顧問弁護士が応対しました。表面上は穏やかな口ぶりでしたが、Cが勝手に行ったことで迷惑を被っているのはB社も同じであるし、B社にはCの行為に対する使用者責任も認められないと強く主張しました。むしろ、あやしい取引に気づかなかったA社にも責任があるのではないかとの指摘さえありました。
そして、B社は、法的責任はないものの、今後A社と取引するときにはA社に利益が多くなるよう有利な条件にするので、それで納得してほしいと提案してきました。
2、Cの行方
交渉中にB社がCの居場所を突き止めたことが判明しました。B社とCが口裏を合わせないように、A社の代表に同行していただいて対応したところ、CはA社の代表とB社の役員の前で、自らが行ったことを謝罪しましたが、それによって得たお金はすべて遊興費に使ってしまったと説明しました。
ベリーベストはA社と相談した上で、個人であって資産の乏しいCからお金を取り戻すことは難しいと判断し、企業であるB社との交渉に注力することに決めました。
3、ベリーベストの交渉戦略
ベリーベストでは、B社と交渉するに当たり、さまざまな検討を行いました。
A社と同様にCから取引を持ち掛けられて被害者となった2社が、すでにB社を訴えたとの情報が入りました。我々の交渉にも影響を与えるため、これらの訴訟がどちら側に有利に動くのかを見てみたいとも思いました。しかし反面、これら2社の請求額はA社の損害額より大きかったことから、B社が訴訟に負けて傾き、倒産してしまうようなことはないかという心配もありました。
さらに、B社が示談に応じない場合には、訴訟で決着をつけるしかなくなるため、訴訟で勝てるかどうか、訴訟戦略と立証の見通しを検討しました。具体的には、Cの肩書やB社内での立場を考慮しB社が承認していなかったとしてもCの行為がB社の行為であると法的に認められそうかといったことや、Cが訴訟でB社に味方しても我々はB社に責任があることを立証できそうかといったことなどです。
検討の結果、訴訟になっても優位に進められるだろうとの結論に至りました。そこで、B社との交渉は強気の姿勢での臨むことにしたのです。
4、ベリーベストによる交渉
交渉に入って数か月が経過した頃、B社は、A社の損害の一部を補填する解決案を提案してきました。すでに2件の訴訟を抱えていたB社は、A社とも訴訟になることを回避したかったのかもしれません。ただ、提示した金額は、A社の損害額の40%を3年間にわたって支払うという内容でした。これに対し、ベリーベストは、検討に値しないとして再度の提案を要求しました。
B社からの再提案は、A社の損害額の50%を支払うという内容でした。A社の要求水準からは程遠い再提案でした。これでは埒が明かないと判断し、ベリーベストから最初で最後の提案であるとして損害額の約70%の金額を提示しました。そして、これに応じられない場合には交渉は終了し、訴訟準備に入ると言い切ったのです。
ただ、実際には、これで終わりにしたわけではありません。B社の再々提案は、A社の損害額の57%に留まりましたので、ベリーベストは、A社と相談した上で、視点を変えた要求をすることにしました。すなわち、B社に所属していたCの問題によって弁護士費用が発生したのであるから、弁護士費用も負担してほしいというものです。その金額は、A社の損害額の約10%に相当しましたので、実質的には損害額の約67%の金銭を要求する内容でした。
このような交渉の結果、最終的には、A社の損害額の約62%の支払いで和解成立となりました。
解決のポイント
和解した内容は、A社にとって、損害額のすべてを取り戻せたわけではありませんが、Cに関する取引で利益を得た時期もありましたので、それを含めて考えれば悪い条件ではありませんでした。訴訟になれば、数年にわたる労力、心労、費用がかかりますし、必ず勝訴するという保証もありません。
そして、何よりも、A社にとってB社は長年の取引先でもあります。訴訟で勝っても、大きな取引先を失うのでは意味がありません。訴訟になっても勝てるであろうという見通しのもとで強気の姿勢で交渉を行いながらも、訴訟に突入することなく決着できたのは、A社にとって最善の結果であったと言えると思います。
当事者であるA社自身と法律専門家であるベリーベストが一緒に話し合い、A社が置かれている法的立場とビジネス的立場を冷静に認識し、それに基づき相手方と交渉し、着地点を見誤らずに最終的な判断を行うことができた結果であろうと思います。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)