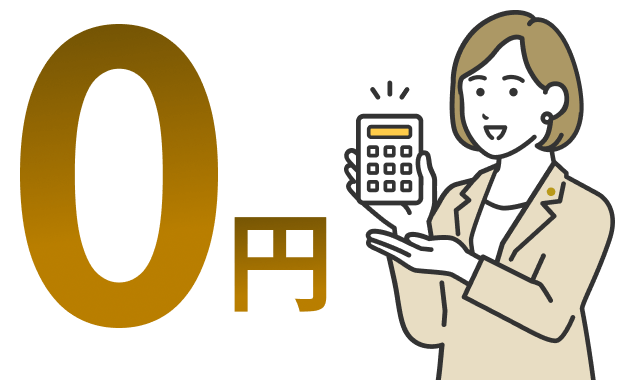円満な相続のために。遺言書の種類や作成時の注意点について解説!
- 遺産を受け取る方
- 遺言書
- 立川
- 弁護士

立川市の平成29年の人口は、18万1554人で、そのうち43,222人は65歳以上であるとの統計が出ています(立川市統計年報(平成29年版)統計表より)。実に23%以上が65歳であり、高齢化が進んでいる現状です。
遺言を遺さずに亡くなってしまった場合に、遺産の多寡を問わず、お金がからむと家族同士で傷つけ合うことになってしまうケースは少なくありません。
そのような事態を防ぐためには、効力のある遺言書を正しく準備しておくことが非常に重要です。ここでは、遺言書の方式や効力のある遺言を作成する際の注意点などを、立川オフィスの弁護士が徹底解説していきます。
1、遺言書を作成するメリットは?
まずは、なぜ遺言書を作るべきなのかを理解しておきましょう。大きなメリットとしては、「被相続人(ひそうぞくにん)」つまり亡くなる人の希望をかなえることができることといえますが、具体的には主に次のようなメリットがあります。
-
(1)遺された家族の相続争いを防ぐ
遺言書を遺さずに亡くなった場合、民法で定められた「法定相続制度」に基づいて相続していくことになります。「法定相続人」の範囲や、遺産相続の割合である「法定相続分」は、民法887条、889条、890条、900条、907条に規定されています。
法定相続制度では、法律は相続する割合だけを決めており、何をどう分けるかまでは定めていません。具体的な財産の分け方については相続人全員で話し合って決めることになります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
どれだけ仲が良い家族でも、この話し合いにおいて、譲れない点や分け方について、争いになることがあります。遺言書では、誰が何を相続するかを決めることができます。遺言書を作成しておくことで、家族間での争いを回避できる可能性が高まります。 -
(2)相続人への財産の分配を自分で決めることができる
遺言書では、介護を担った親族や、教育費がこれから多くかかる親族に多く配分したいなどの希望を相当程度反映させることができます。正式な遺言書を遺すことで、法的な効力を持たせることができるのです。
財産を成した被相続人本人の意思を優先できる点が、遺言書作成における最大のメリットともいえるでしょう。 -
(3)法定相続人以外にも財産を分配できる
法定相続人でなくても、お世話になった人や慈善事業などに財産を分配できることも、遺言書を作成するメリットです。生前収集したコレクションなどを、価値の分かる知人や団体に寄贈するといった指定も行えます。
たとえば「長男の嫁」は直接の子どもではないため、法定相続人に入りません。しかし、「ずっと世話をしてくれたので、長男の嫁に相続してもらいたい」という場合は遺言が必要です。
2、遺言書の方式とメリットとデメリットとは
遺言書の方式や効力については、民法第960条から第1027条において、詳細に定められています。ここでは、平成30年12月時点で法的に認められている遺言書について解説します。
遺言書は、遺す状況や作成方法によって、3種類の普通方式と4種類の特別方式に分けられます。
-
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言の内容を自筆で書面にして、署名と押印をすることによって作成する遺言です。メリットは、紙とペンと印鑑があれば自分ひとりですぐに作成できる、といった簡便さが挙げられます。
自筆証書遺言の最大のデメリットは、形式や手順のミスにより無効となる可能性があるという点です。たとえば、あくまでも自筆で行われることが必要であるため、パソコンなどで入力し印刷したものでは認められません。また、自筆証書遺言は、相続を開始するときに、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に対し、正しい遺言の方式で記載されているか確認を求める「検認」の手続きを請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。検認を経ずに封印のしてある遺言書を開封した場合、「過料(かりょう)」と呼ばれる罰金に処されることになります。
なお、平成30年7月6日の民法改正により、パソコンなどで作成し印字した財産一覧や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を財産目録として添付することが認められることになりました(改正法968条2項・平成31年1月13日施行)。ただし偽造や改ざんを防ぐため、各ページに自署押印が必要です。
また、これまで自筆証書遺言は、作成者の責任で保管するため、紛失のおそれがありました。しかし今回の法改正により、法務局での自筆証書遺言の保管が可能となります。法務局で遺言書の保管をする場合、検認は不要です(「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」)。ただし、本法律の施行日は平成30年7月13日より2年以内となっており、まだ施行日は決定していません。施行前は法務局に保管することはできませんので、注意が必要です。
詳細については、遺産相続事件に対応した経験が豊富な弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(2)公正証書遺言
公正証書遺言(民法第969条)は、公証人および証人が内容の証明をする遺言書です。作成時には2名以上の証人の立ち会いが必要です。自筆証書遺言と比べてやや手間と費用がかかりますが、専門家である公証人が作成するため、形式不備によって無効となる心配がありません。また、原本は公証役場で保管されるため、改ざんのおそれもありません。公証手続きを経ているため、相続開始後の検認手続きも不要です(民法第1004号第2項)。
公正証書遺言の場合、仮に遺言者が署名することができない場合には、公証人がその旨を記載すれば、署名に代えることが可能であるため、身体に不自由がある場合にはこの方法で遺言書の作成が可能になります。
ただし、証人を依頼したり、関係書類をそろえたりなどの準備や、公正証書を作成する費用が必要になる点が、デメリットと考える方もいるようです。公正証書遺言の作成についても、事前に弁護士などの専門家に相談や依頼することで、スムーズな作成ができるでしょう。 -
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言(民法第970条)とは、公証人および2名以上の証人が、遺言の存在と、それが本人の書いたものであるという事実のみ証明します。したがって、内容自体は誰に対しても秘密にしておくことができます。
しかし、遺言書の存在を公証人や証人に証明してもらうための費用がかかるものの、自筆証書遺言と同様のデメリットがあります。遺言書作成時に内容の確認ができないため、開封時は家庭裁判所の検認が必要です。検認を経ずに勝手に開封した場合、「過料」が科されることになります。検認の際に形式上の誤りが発覚し、無効になってしまうことも少なくないようです。
内容を秘密にしたい場合でも、作成の際は経験のある弁護士などの専門家へ、事前に相談したほうがよいでしょう。弁護士であれば守秘義務があり、相談の内容を漏らすことはありません。 -
(4)特別方式遺言書
特別方式遺言書(民法976条など)は、死期が迫っているような状態であるときに迅速かつ簡易な方法により遺言書を作成することが認められる特別な方式です。特別方式の遺言には、「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。
これらはそれぞれ危篤のとき、遭難したとき、伝染病で隔離されているとき、船上にいるときの例外的な場合に認められる遺言です。遺言者が普通方式の遺言書ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、効力を失います。
3、遺言書において法的に効力を持つ内容とは
遺言書に記載する内容に、特に制限はありません。しかし、法的に効力を持つ事項は、主に「財産に関すること」「身分に関すること」「手続きに関すること」に限られています。法律で定められたこれらの「遺言事項」以外は、遺言書に記載しても法的な強制力はありません。
ただし、遺言事項以外のことに関しては「付言事項」として書き残すことが可能です。法的な効力はありませんが、なぜそのように相続するよう指定をしたのかなどを付記することによって、より円満な相続となる可能性があるでしょう。
-
(1)財産に関すること
財産に関して、具体的に、誰に、どのくらい、どのような分け方で相続させるかを指定することができます。相続人の個別の事情に応じた相続分を、被相続人の意思で示すことができます。
-
(2)身分に関すること
「認知」、「未成年後見人・未成年後見監督人の指定」など、遺された家族の身分に関することを指定することができます。被相続人に、生前は認知できなかった子どもがいて、その子どもにも相続させたいときなどは、遺言によって「認知」するよう指定できます。認知された子どもは法定相続人となり、財産を相続する資格を得ることができます。
また、被相続人が亡くなることによって親権者がいなくなる子どもがいる場合には、未成年後見人の指定もしておくことができます。 -
(3)手続きに関すること
相続の手続きを行う「遺言執行者の指定・委託」と、「祭祀(さいし)承継者の指定」ができます。
「遺言執行者」とは、土地の登記名義や銀行口座の名義変更など、相続に必要不可欠となる事務手続きを行う者です。遺言執行者は、家族だけでなく、弁護士や行政書士など第三者を指定することもできます。ただし、未成年の子どもや破産者などは指定できません。「祭祀(さいし)承継者」は、神棚や仏壇、お墓などを管理する方のことです。
4、遺言書の効力が認められないケースとは
遺言書をせっかく作成しても、特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は、要件を満たしていないことに気づかず、その効力が認められず無効になってしまうケースもあります。
以下に、起きやすい間違いを紹介します。作成する際には注意するようにしましょう。
-
(1)被相続人が遺言書を有効に作成できる能力・状態にない
遺言の作成には、被相続人自身の意思能力(事理弁識能力)が必要です。被相続人は、満15歳以上である必要があります。幼過ぎると自分の財産の処分を適切に判断できないとみなされ、遺言は無効となります(民法第961条)。
また、認知症の状態で書いたとする遺言書は無効とみなされる可能性があります。なお成年後見人が就任している成年被相続人については、一時的に自身の意思能力や判断力が回復したときに、2名以上の医師の立ち合いなどによって作成した遺言書の効力が認められます(民法第973条)。 -
(2)法で定められた書式や作成手順が守られていない
遺言書に法的な効力を持たせるためには、法で定められた作成手順でなければ効力を失います。具体的には、以下のような不備で無効となるケースがあります。
- 自筆証書遺言が本人の手書きでない
- 日付がない、または「◯年◯月吉日」などになっており特定できない
- 署名・押印を忘れてしまった
- 押印の印影が、封緘(ふうかん)と本文で違う
- 公正証書遺言、秘密証書遺言の証人の身分が不適格だった(民法974条)
- 記載されている財産額と現実の財産額がかけ離れている
なお、公正証書遺言や秘密証書遺言で求められる「証人」には、民法によってその範囲が定められています。もし、証人を依頼できる人物がいなければ、公証役場や弁護士に依頼することが可能です。
-
(3)遺言書の作成に本人以外が関わっている
遺言書は、他者からの影響を受けずに意思を示したものである必要があります。民法第975条では、「2人以上が同一の書面で遺言を作成することはできない」と定められており、夫婦連名による「共同遺言」も、法的には無効です。他人の代筆による「自筆証書遺言」も、本人以外が関わっているという理由で無効になります。
詐欺や強迫によって記された遺言書も、本人の意思が適切に反映されたものではないため無効となります。
5、まとめ
遺言の作成は、遺された家族の精神的負担を大きく減らすメリットがあります。また、自身の財産や意思の棚卸しをすることで、家族との関係性を見直し、やり残したことも明確になり、より有意義に人生をまっとうするきっかけになるのではないでしょうか。
一方で、専門的な知識やサポートが必要な作業が発生することもあるでしょう。書式、手続きについては、相続問題に対応した経験が豊富な弁護士や税理士に、確認したほうが安心かもしれません。遺言書の文言を訂正する方法も細かく決められているので、書き間違えたり、訂正したりする際には注意が必要です。
特に現在は、法改正と施行のはざまの期間です。常に最新の状況をキャッチアップしている弁護士のアドバイスを得ることで、確実に遺言書を作成できます。
遺言書の作成を検討したい、相談したい方は、ベリーベスト法律事務所・立川オフィスへ連絡してください。ベリーベスト法律事務所であれば、行政書士や税理士をご紹介することも可能です。遺言書の作成から、生前分与、相続税対策など、相続に関して多角的な提案を、他士業とも連携をとり対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています